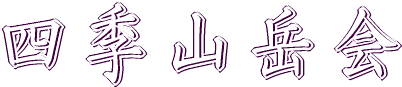大峯奥駈道(五番関~前鬼)
【1日目:5/29】
下市口駅からバスで洞川温泉(10:45)・・・五番関登山口(12:25)・・・洞辻茶屋(14:00)・・・山上ヶ岳(15:40)宿坊泊
【2日目:5/30】
山上ヶ岳(05:40)・・・大普賢岳分岐(07:50)・・・国見岳分岐(08:35)・・・七曜岳(09:30)・・・行者還岳(10:35)・・・奥駆道出合(13:10)・・・弥山小屋(15:30)泊
【3日目:5/31】
弥山小屋(06:00)・・・八経ヶ岳(06:35)・・・舟ノ垰(08:36)・・・孔雀岳付近(11:05~12:00)・・・釈迦ヶ岳(14:20)・・・太古ノ辻(15:50)・・・小仲坊(18:05)泊
【4日目:6/1】
小仲坊(07:20)・・・前鬼口(09:50)・・・帰途へ
先月に続く奥駈道の縦走(その2)。五番関に登り返し、女人結界門をくぐって山上ヶ岳へ。洞辻茶屋で日帰りの2パーティと出合い、その上で日白装束の講参り組みとすれ違う。山頂、夕方近くの本堂周辺は静まりかえっていた。本堂で蝋燭2本を灯し、Uさん、Kさんの2人を無事導いてくれるよう祈る。泊まった桜本坊の客は私一人。風呂に入って質素な夕食をいただき、早めに寝る。夜は結構な雨と風が窓バラスを叩き続け、重たい布団も寒かった。
2日目は弥山まで16.7km(水平距離)、10時間。後半の奥駆道出合い辺りから左膝が徐々に痛み始め、最後の弥山小屋へ至る300m超の登りに少々時間を要した。終日雨予報だったが、朝方の小雨は間もなく止み、途中では日が差すこともあり、ゴールまで穏やかな天候だった。所々、展望が利いて、前後のピークを望めることもあった。新緑が美しく、行者還岳前後からはシロヤシオとシャクナゲに癒やされる。縦走路は幾つものピークを越えたり巻いたりしながら付けられており、岩場が露出する各ピーク付近は鎖やハシゴが十二分に用意されている。それ以外は歩きやすく気持ちの良い尾根道を楽しめる。この日、出会ったのは日帰り組みの数パーティ。弥山小屋の客は今夜も私一人。膝にあてる湿布薬をもらい、暖かい食事をビールと共に楽しんだ。ビールと翌日のパンを含めても9500円。北アルプスの小屋と違って安い。夜は本格的な雨が降った。
3日目は前鬼まで13.8km(水平距離)、9時間の予定を12時間も要した。未明から強風。時折、暴風。雨ではないが濡れる。ドコモの電波の届いた小屋で天気予報を確認し、計画通り進むことを決める。西風なので尾根の左側にいる間以外はずっと右側からの強風を受けて歩いた。奥駆道の最高峰、1915mの八経ヶ岳から先は釈迦ヶ岳までは歩く人が少ないのだろう、道が細くなって踏み跡も薄い。それまで分かりやすかったピンクテープもまばらになる。迷ったような踏み跡に獣道が交錯するので、幾度もルートを外したり戻ったりしながら進むことになった。寒くて震えが出そうになり、雨具の下にダウンを着込む。眺望がないどころか、視界はガスで50mくらい。地形図からは分からなかったが、昨日のような穏やかな尾根道よりも両手を使って上下する岩場が主体となり、再び痛み始めた左膝を気にしながらの少々厳しい展開になってきた。予定時間から徐々に遅れが出ていたものの、まだ余裕はあった。ところが、修験者の業場のある孔雀岳の巻き道で予想外の事態に陥った。道迷いである。
強風で雨具のフードをかぶっていたために左へUターンするように登るルートが見えなかったのか、代わりに真っ直ぐ進んでしまった。倒木を越え、苔むした岩と杉林の中に誘い込まれ、しばらくしておかしいと気付いた。鉄則通り戻ろうとしたが、戻りかけても来た道がまったく分からない。GPSによれば左手の上の方に登山道があることになっているが当てにできないし、下手にショートカットを試みても傷を深くするだけだ。明るいうちに前鬼にたどり付けなければどこかで夜明かしもあり得る。杉の林が強風でうなりをあげる中、この状況はヤバいと心底思った。結局、行きつ戻りつ上下しながらしっかりとした踏み跡に戻ったときには嬉しくて絶叫した。1時間近くが経過していた。
復帰地点から先、おかしなことに見覚えのある風景が次々に現れた。どうやら戻りすぎていたようだ。そして、再び先ほどの杉林の入口に出くわした。ここでようやく左手にUターンする踏み跡に気付き、本来のルートに乗った。釈迦ヶ岳への急登をがんばって進み、山頂にある釈迦如来立像の後ろ姿が見えたときは思わず雄叫びを上げた。予定時刻を2時間20分もオーバー。膝痛がひどくなったが気持ちを強く持って着実に下るしかない。釈迦ヶ岳で向こうから上がってきたテント装備の若者一人が本日出会った唯一の登山者。彼は引き返して深仙の宿に泊まると言い、どんどん下りていった。
深仙の宿あたりは、奥駈道を開いた役行者の修行の場。感慨に浸る余裕もなく先を急ぐ。太古の辻から尾根を外れて左手の急斜面を下る。3時間オーバーで薄暗くなったころに前鬼の小仲坊にたどり着く。軒先から到着を告げると、来た来た!と奥からが大きな声が聞こえて宿の夫婦が飛び出してきた。ありがたいことにまず風呂に入るよう促され、すっかり暖まったところでビールと共に心のこもった料理をいただく。この宿の夫婦は、1300年前に役行者に付き従った前鬼、後鬼の子孫で61代目。当時、山人は鬼と呼ばれていたらしい。鉱物をふくめ山中の資源に精通し、私財を肥やした人もいて、それをやっかんだ呼称でもあるとか。前鬼と後鬼は役行者のサポート役となって修験の道に入ったという。同宿者2人と飲みながら、修験道にまつわる様々な話を聞かせてもらった。大阪の自宅から3時間半をかけて毎週末、この宿坊を開き、守り続けている。
翌朝はすっかり晴れた。バス停のある前鬼口まで林道を歩いて2時間半。バスが来るのは5時間後。いったん反対方向のバスに乗り、近くの温泉地で時間を過ごして帰りのバスに乗ることができる。ベンチでバスを待っていると大阪からの同宿者の一人がクルマで下りてきて、なんと駅まで送ってくれると言う。駅までの道中、宿の女将さんが私の到着の遅れをいかに心配していたか話してくれた。彼は北アルプスよりも大峯のほうが怖いと言う。登山者は少ないし有人小屋がほぼなくエスケープも困難。帰ってから調べると前鬼までの道迷い事例が多々あることが分かり、無事に下りられたのは幸運だったと心から思う。全長90kmの奥駈道の北半分を歩いたことになるが、残りの南半分をどうするか、ゆっくり考えることにする。