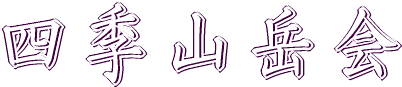南アルプス 甲斐駒ヶ岳
22-0724 5:50調布駅集合 8:30尾白渓谷駐車場 15:40七丈小屋予定
先週、御嶽山に登った。行程の80%ほどが曇りガスの中で気温は高くなかった。それにも関わらずかなりばてた。同じような時間山に登ってもばてる時とそうならない時がある。理由は完全には分からない。
そのため甲斐駒ヶ岳山行への参加の可否は直前になって考えざるを得なかった。甲斐駒ヶ岳は以前から行きたい山だった。日向山からの甲斐駒ヶ岳の厳しい姿が目に浮かぶ。行きたい。しかし体力はどうだろうか。多少遅れてもたどり着ければ良いのだが。途中でだめになればおそらく全員が下山することになる。その迷惑はかけたくない。好天に恵まれればかなり暑い。御嶽山の倍ほどの時間歩かなければならない。
このような悩みを昔は持ったことがなかった。やはり・・・・いやそれは言うまい。言いたくない。しかし現実は受け入れないと物事を間違える。
7月20日水曜日の段階で、参加取りやめを決めてラインをした。
私の参加取りやめのラインを受けて皆さんからの「途中でだめになればなったで良いじゃないですか。」の言葉はありがたかった。また「せっかく皆さん月曜日休んで計画したので全員参加できるよう行き先を変えましょうか?」の言葉には「そんなことは楽しみにしてらっしゃる皆さんのことを考えると申し訳なさ過ぎる。(変な言葉遣い失礼)」「それなら出来る限りがんばってみよう!!」と気持ちを切り換えた。
対策を考えてみた。自分としては御嶽山のバテの原因の第一は、ジムと考えた。御嶽山の一週前に塔ノ岳に行き、下りで結構疲れてそれを言い訳にジムをサボりがちになった。そこで、①やり過ぎに気をつけながら、ジムに行って右膝の痛みで止めていた、スクワットを15㌔で再開した。②山行の後2日は休めと言われていたのだが、これを止めて翌日からごく軽く運動することにした。こうした方が調子が良い。③アミノバイタルを山以外の日でも飲むことにした。④荷物を出来うる限り減らすことにした。⑤軽量ザックの肩の部分が痛むのでパッドを入れた。これらのことは甲斐駒ヶ岳不参加を表明する前から始めていたこともある。これらのことをして当日を迎えた。
調布集合、全員そろって6:00前には出発、5:50だったと思う。長丁場、厳しい登山路を意識してなるべく早く着きたいとの気持ちが皆にある。
8:00ぐらいに尾白渓谷駐車場到着。以前ここから雪の降った翌日に日向山に登った。その時の甲斐駒ヶ岳が実に良かった。沢筋に雪を積んで薄くガスが吹いていた。堂々としてとても大きく厳しい姿だった。登りたいと強く思った。
さらに黒戸尾根を歩いてみたいとの思いもあった。日本三大急登と呼ばれまた長い。甲斐駒ヶ岳の表登山道でもある。百名山でもある。登れれば57座目となる。
尾白川渓谷駐車場、竹宇駒ヶ岳神社の横から尾白川にかかる吊り橋を渡る。きれいな川だ。尾白川渓谷道を分けて登っていく。ややしばらく登って一合目と言われる小さな石造りの社がやっとあった。屋根に苔が載せたように生えている。笹の平分岐、甲斐駒ヶ岳まで7時間とある。笹の平、二人男性が休んでいる。ここから八丁登り、美しい樹林の中の長い登り、さらに進むと樹林が開けて岩場、急に尾根が狭くなり刃渡りの岩場、転落防止の鎖が張ってある。正直に言ってこういうところに恐怖感を持つことはいつからかほとんどなくなってしまった。今回の皆さんおそらくそうだろう。鎖場、梯子がしばらく続き高度を稼ぐ。登り切って刀利天狗、社が二つ石碑が沢山建っている。何か天狗の親分が住んでいそうだ。社を見る度に思うが諸々の神様や天狗様は4時限以上の世界に住んでいるのだろうから、見た目は小さな社でも神様天狗様の世界ではそれは大きい立派なお屋敷になっていてそこで宴会したり踊ったりしているのだろうなと想像する。また女神様が奉られている社はいかにもそれらしく優雅に造られており楽しい。
ここから大きく黒戸山を巻いていき、五合目小屋跡になる。そのあとは屏風岩の登りとなる。山になっている巨大な岩の麓、ここにも社や沢山の石碑が風雪を経て建っている。岩自体にもしめ縄が張ってある。オーバーハングしておりこちらに迫ってくるようだ。右側に梯子鎖場が見えている。地図を見ると五合目、等高線が密で黒っぽくなっている。
14:40七丈小屋到着。出発が1時間弱早かったので時間通りだ。約6時間なかなか良いペースだ。しかしやはり結構疲れた。みんな小屋のベンチでしばし休憩。七丈小屋は山の斜面に建っているように見える。登山道に沿って立っており平坦地に立っているのではない。冷たい水が出しっぱなしになっていて隣ではその水でビールやコーラ、ジュースを冷やしている。500㍉㍑のスーパードライ800円なり。
小屋内に入り荷物をざっと片付ける。二階の寝床は一人一人ビニールなどで区切ってある。敷き布団と枕がある。私は本日軽量化のためシュラフを持たずカバーと衣類で寝る。
下に降りて乾杯、お疲れ様でした。参加を取りやめにしないで良かったとつく尽く思う。
大嶌さんとつぼさんはスーパードライを飲み干して持参のワインと焼酎をやっている。
一泊二食付き9500円、消灯20:00、明日は4:00行動開始なので3:00起床、朝食はお弁当にして夜の内に作っておいてくれるそうだ。
からだがベトベトするので冷たい水でタオルを絞って拭いた。翌日尾白川渓谷駐車でつぼさんがからだを拭いている身体用ウエットティシューをもらって拭いてみたところなかなか良い。今度からはこれにしよう。
今日の私の寝具はシュラフカバーと下は冬用ロングパンツとズボン、上は沢用ファイントラックの下着、その上に冬用長袖シャツ、山用ワイシャツだ。ダウンのジャケットとカッパは掛け布団にして明け方少し使った。ちょうど良かった。7月下旬の七丈小屋での泊まり。
夕食後下でお喋りをしていたが大嶌P以外の人達はソロの方が多くお話をしている方はいなかった。泊まりは日曜日なので全部で8人ぐらいだったかと思う。
22-0725
4:00七丈小屋 6:00甲斐駒ヶ岳山頂 7:40七丈小屋 12:05尾白渓谷駐車場予定
大嶌Pは3:00に皆起き出した。昨夜20:00就寝なので一応名目7時間寝ていることになる。大嶌さんは生あくびをしている。いびきと寝言がうるさく余りよく眠れなかったそうだ。「テントの方が慣れていて良い。」と言っていた。テントでも小屋でも寝言のうるささはあまり変わらないようにも思えるが。
荷物は小屋から山頂までの往復に必要なものだけを持って行く。2人はサブザックで2人はポリ袋に持って行かない荷物を取り出し、来た時のザックで行く。
山小屋は頂上直下や山頂まで30分ぐらいの小屋が多いのではと思うが、七丈小屋は七合目に有る小屋だ。何となく荷を軽くして山頂を目指すとなると気持ちが楽になるが、まだここから片道2時間有るのだ。明けるまではヘッデンを点けていく。
準備を整え朝食を摂る。舟久保さんは朝食のおいなりさんを食べている。私はおいなりさんとパンを一個。このパンだが「山崎パン」総菜パンでも3日甘いパンだと5日ぐらいももつのだ。私は今回荷物を軽くするためお湯を使うカップ麺やジフィジスの米などは持たず全てパンにしたのだが、日持ちが良いのでとても助かった。ただ5日ももつパンにはそれなりの薬品が使われているとは思う。ミスターさだでもいれば何度も聞いた食品についての講釈をまた聞かされるところだ。
昨日、山頂でご来光を仰ぐとすれば2:30ぐらいに小屋を出れば良いでしょうと、小屋番から聞いてる人がいたが2:30行動開始では1:30に起床しなくてはならない。そんなことをする人はいないのではとその時思ったが、登って行ったところ途中で出会った女性が小屋から登ってきていた。女性ソロ。舟久保さんが「女性で一人この道をヘッデンですごいなあ。」と感心していたが、小屋から頂上に至る道はへッデンで行くのはなかなか難易度が高い。梯子くさり場が結構ある岩場の道だ。すごい。経験豊富なかたなのだろうと思う。中年の小柄な女性でした。いずれ舟久保さんもその女性のようになるのではないだろうか。先ほどの舟久保さんのつぶやきには尊敬の念と、あこがれが混じっているように聞こえた。
テン場のわきを通って梯子くさりを掴んで岩の間を高度を稼いでいく。ハイマツが多くなり振り返ると展望が良くきくようになってくる。眼下には一面の雲、東の空があかね色に染まる。まだ陽は昇らない。日の出に急かされるように登る。たびたび振り返る。
岩に一本剣が刺さっている。わずかに明るくなった空を背景にして不思議な図だ。
ついに陽が昇る。一気に明るくなる。やっぱり何度見てもご来光は良い。雄大壮大な美しい光景だ。大嶌Pはみんな赤く染まりながら太陽を見ている。陽はすぐに昇り見ているのが明るすぎて辛くなる。八合目の緩い傾斜を持った台地にでる。昔は講中のご来迎場であったらしい。すっかり明けた空は甲斐駒ヶ岳をはっきりと見せている。いや頂上はもっ
と奥か。さらに登り続け遥か上に見えた烏帽子岩も下に見える。ついに甲斐駒ヶ岳の頂上に至る。
大きな景色は様々な山で経験しているつもりではあるがやはり大きい。360°の景色だ。目の前に多くの山山が姿を見せてくれている。北岳、仙丈ヶ岳、鳳凰三山、鋸岳、はるか下に日向山、富士山も、北には八ヶ岳が大きく全貌が見える。
先に到着していた女性が「降りたくない。」と言っていたが実感だ。いつまでも飽きることはない。確かにこの時間を求めて登ってきたのだ。とも言える。毎回このような素晴らしい光景が見られるわけでもない。写真でも見られるけれど、自分の足で登ってきて天候に恵まれて見る山々はまた違う魅力を持っている。
下山路は結構長かった。月曜日という事もありつぼさんの携帯電話が何度も鳴っていた。現役は忙しい。朝4:00行動開始尾白川駐車場着15:25
今回の甲斐駒ヶ岳大成功の山旅でした。大嶌リーダーつぼさん舟久保さんありがとうございました。