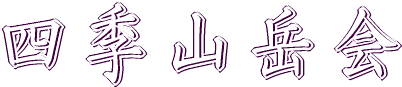表妙義(白雲山→金洞山)
○12/15(日):(圏央道)日の出IC:0430→(上信越道)松井田妙義IC:0600→道の駅みょうぎP:0630→妙義神社:0645→大の字:0730→奥の院:0800→見晴:0840→ビビリ岩→大のぞき:0925→天狗岩→相馬岳:1030→バラ尾根→堀切:1115→鷹戻し:1300→東岳(金洞山)→中ノ岳:1500→主脈のコル:1545→中間道(関東ふれあいの道):1600→中ノ岳神社:1630→(タクシー)→道の駅みょうぎP:1700→(温泉・ごはん)→帰京
次に登る方々の参考に、
1.この時期は服装が一番気になります。
登り下りが激しいので、汗をかきます。
一方で、尾根に上ると北風にさらされていきなり寒くなります。
(私たちの山行では9時までは強風でしたが、それ以降風が弱まり、最高のハイキング日和になりましたが。)
毛局、薄手のインナーを数枚着て、ライトダウンとウィンドブレーカを持ち、休憩時に服装調整することになります。
下ってからも、中ノ岳神社から妙義神社までのタクシーを待つ時間が長く、結構冷えます。
2.手袋については、岩登り時のホールド感は素手のほうが確実ですが、素手で鎖を持つのは冷たいので必要です。。
ちなみに、リーダーはワークマンの作業手袋、Kさんは皮手袋、Hさんはラバーの手袋、私は滑り止めのイボイボ付き軍手をしていきました。
鎖と手袋の摩擦は必要ですが、鎖を手の中で滑らせながら登っていきますので、あまり粘着力が強いと危険です。
リーダーは数回登ると手袋が痛むので、消耗品感覚で選んでいるとのことです。
私は何回も使って洗い、粘着力が弱くなったイボイボ手袋を使いました。
3.靴については、Kさんはなんと沢靴のラバーソールを履いてました。(両神山に次いで2回目)
フリクションが効くので岩登りに適しているとのことです。
しかし、表妙義は岩場だけではなく、砂地の急下りもありますので、靴底に大きな凹凸のない沢靴は万能とはいえません。
岸壁は溶岩の固まった岩で、結構フリクションが効きますので、靴は履きなれたトレッキング用で十分だと思います。
10時間弱の縦走になりますので、長丁場で足やひざへの負担も大きいです。
4.鎖への自己ビレイの仕方は大きく分けて
A 鎖の長円の輪の中に小さな(細い)カラビナを掛けて、登るにつれ、カラビナを短ピッチで上へ上へと架け替えていく方法
B 大きなカラビナを使って、その中に鎖を通して、山側の鎖の支点まで登ったら次の鎖に付け替える方法
の2つがあると思いますが、自分で経験してみて、表妙義はBの方法が適していると思いました。
Aの方法は自己ビレイとして確実ですが、欠点は鎖の輪が小さいとカラビナを付け替えるのに手間がかかり、腕力を消耗することです。
岩登りの途中でも、短ピッチでカラビナを架け替える必要があります。
岸壁でカラビナを架け替えようとすると、岩に体を近づけることになり、足が滑り易くなります。
それを止めるために腕力で鎖に頼るという悪状況になります。
特に、鷹戻しに掛けられた鎖は古いので鎖の輪の溶接部が太く、輪の内径が小さくなっています。
それまでの岩場では、それなりに架け替えられたカラビナですが、ここでは鎖の輪から抜きずらく、岸壁の途中で格闘する羽目になりました。
リーダーのアドバイスに従って、途中でBの方法に変えたら、カラビナを気にせず登れるのでなんと楽なこと。
ちなみに、へそ曲がりの私以外は最初からBの方法で楽に登ってました。
鎖の支点は、たいてい足場のしっかりした場所に作られていますので、カラビナの架け替えもスムーズです。
Bの方法は、自己ビレイといっても、落ちたら谷側の鎖の支点まで滑落するので、体は岸壁にたたきつけられますが、死亡は免れるという保険です。
それでも、Aの方法で登るのに比べると、腕力の消耗がなく登りやすいのでトータルとして適していると思います。
登っている途中で休憩したい場合は、Aの方法で自己ビレイを確実にとるのがよいでしょう。
5.最後に、腕力は使い切らないように、鷹戻しまではなるべく温存しましょう。