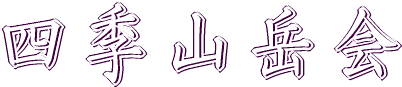梓川源流・二ノ俣谷遡行(8月11日)
8月10日(快晴) 調布5:30=沢渡=10:30上高地バスターミナル10:40~13:15横尾(道間違え80分ロス)15:03~16:08二ノ俣谷出合い(テント)
8月11日(快晴のち曇り) テント6:45~15:58登山道(大天井ヒュッテの東側)16:15~16:45大天荘(テント)
8月12日(晴れ) テント5:35~8:40西岳ヒュッテ9:05~10:07水俣乗越~18:15上高地
午前5:30起床、沢支度に着替えて出発。
ザックの重さは、自宅を出るときに量ったときには11kg、それに4人用テント一式を加えて13kg。
13kgのザックを背負って沢登りしたことはなかったので不安はあったが、なんとか最後まで持ちこたえた。
重い荷物を背負って、標高差1200mの沢を登るのは容易ではない。
更に、沢の水が涸れる直前に沢水2リッターづつ酌んでザックにいれ、崖状の露岩を這い上がっていく。
その詰めの長かったこと。
全体を振り返ると、ゴーロ、小滝、草付きの悪場の高巻き、ナメ滝、雪渓、崖部と続き、沢登りというよりも沢旅といったほうがぴったりする行程でした。
反省点としては、
1.渡渉時に必要になるといわれたストックを持っていかなかった。
沢の水量が多くなかったので実害はなかったけれども、リーダの指示には従わないといけません。
2.滝の登りで岩のステップに土が積もっているのに、足を載せて踏ん張れず、滑って滝つぼの中に落ちてしまった。
土にはフリクションは利きません。
3.沢登りに13kgはやはり重過ぎるので10kg以下に抑える軽量化が必要。
次に登る方々へのアドバイス
1.このルートは体力が必要
2.十分な経験があり、突破力とルートファインディングの長けたリーダーが必要
3.雪渓から沢に降りるエッジ部分は裏面が溶けて薄くなっているので、木を置いてそこに体重をかけるなどの工夫が必要。